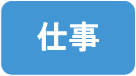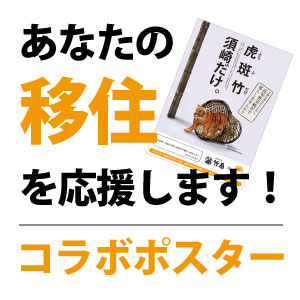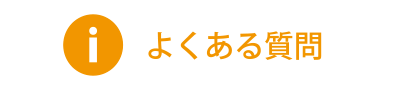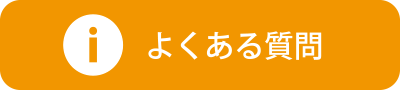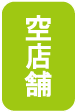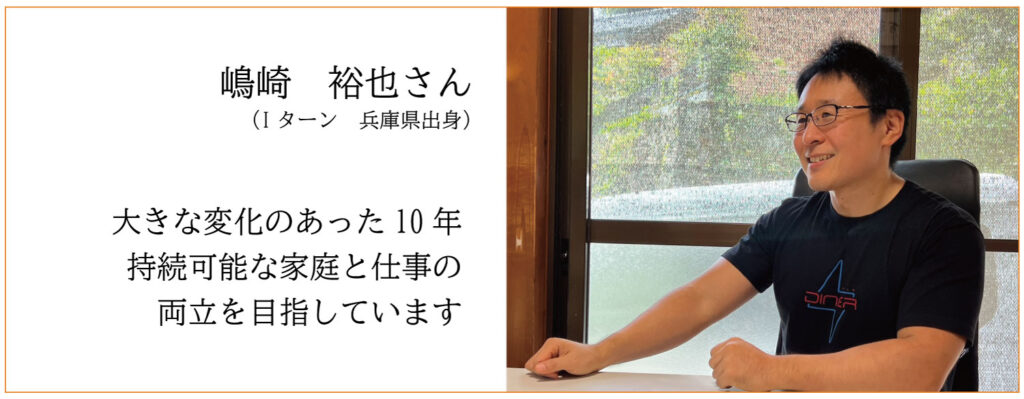
2010年に須崎市へ移住し、2012年にEarth Aid(アースエイド)を創業。ぬたの製造、販売を始めた嶋崎さんに、10年ぶりにインタビューを行いました。ご結婚、お子さんの誕生、仕事の海外進出。多くの変化が訪れた嶋崎さんに現在の暮らしについて聞いてみました。
―――大きく変わったところはやはりご家族が増えたことでしょうか。
移住したての頃は独身でしたからね。35歳のときに結婚して、現在は子供が4人います。上は8歳、下は2歳です。独身から一気に6人家族なので、仕事よりも生活の部分が大きく変わりました。

―――働き方にも変化はありましたか?
独身の時は1日15、16時間、月の残業時間でいくと300時間から400時間働いていましたが、子供が3人、4人となるとそれは無理です。大家族のように両家の祖父母の協力を得られない核家族では、物理的には無理じゃないかなと思います。自分が大変か大変じゃないかよくわからなくなっているのが、今の状況です。(笑)
でも、暇すぎてどうしようかなとなると人間ろくなこと考えないので、子供がいてイベントがどんどんあって変なことに悩む時間もないということは、ある種、健全かもしれないですね。
自営業では、自分を守るのは自分しかいないので、自己管理として筋トレをしています。前にインタビューを受けたときは、結構お酒を飲んでいましたけど、子どもを風呂に入れてとか寝かしつけしてってなってくると、お酒を飲んでいる時間はないです。子供は夕方になったら必ず帰ってくるし、風邪ひいて帰ってくるとか、怪我して帰ってくるときもあるし、それに対してうまく回すのが、僕個人の命題ですね。家庭と仕事の両立、それと自己管理をし始めたことも大きな変化です。
―――お子さんの将来も楽しみですが教育やお金についても気になりますか?
子供にかかる教育費で親は”おじる”(高知の方言で怖がるの意味)。一人2000万。うちでいうと8000万。冷静に考えたら、そりゃおじます。勉強するのは情報のインプットだけなので、豪華なキャンパスに行くのがゴールじゃないと思っています。学歴という看板が欲しいなら別だけど、本当に大事なものは手に職。であれば、技能実習的なものなのではと思っています。今なら家でも情報収集できたりしますしね。
教育そのものにお金をかけることがゴールではなくて、自分自身がやりたいことを見つけたり、手に職をつけたり、オンリーワンの価値を生み出せるようなものを身に着けることが大事なはず。だとしたら、AIの技術も進んできているので、教育費に対してそこまでナイーブにならなくてもいいかなと思います。人間が人間らしくメンタルを維持しながら、幸福感を噛みしめて生きていくことが大事だと思います。
―――起業してから12年、現在のお仕事は順調ですか?
リーマンショックもあったりして、国内の不景気もあり、どこも大変です。この間もロサンゼルスに営業に行っていました。日本から海外へ向けて仕事している人は、国内だけじゃ足りないから、海外に攻めてるわけです。国内の販売が落ちてきているのはどこも共通の課題で、同じことをしていても、人口が減っているので、可処分所得もないから物理的に仕方がないんです。
国内のアンテナショップで販売に苦労しても、外国人がたくさん乗っている高知港のクルーズ船だと3、4時間で50〜100個売れたりします。日本と外国で所得の差が開いているから、日本で1000円の価値のものが、外国人からすると300円くらいなんですよね。激安だという感覚なので、ある程度納得いくものだったら飛ぶように売れます。
―――黒にんにくや、ぬたは外国の方のお口に合うんですか?
合うみたいです。実際に食べてもらうと「Amazing!」と言ってもらえます。黒にんにくは20年くらい前に三重大学の先生が発明したもので、まだ黒にんにくを知らない人が多く、日本人でも知らない人が多いですよね。僕も知らなかったですし。
試食してもらったときに「これは美味しいし、100%オーガニックだし、甘くてしかもニンニクだ」と。ニンニクが体にいいという意識は、日本人よりも欧米人の方が持っています。ガンの抑制作用があるということを、教育で学んでいる。向こうは医療保険がないから、一回病気すると数百万かかる世界です。性能が良くないと売れないので、サプリメントもすごく利くんですよ。サプリや食で健康を維持し、どうやったら病院に行かずに済むかを考えています。
所得の問題と、食文化の洗練があるから、良いものが売れやすいんです。そこに活路を見出して、日本で落ち込んでいる分を修正しています。
―――海外への進出は県が主導しているのですか?
県主導のものもありますね。農水省がやっている支援事業、補助事業、コンサルを率いて取り組んでいる事業に行ってみて情報提供をいただくなんてことも一部あるけど、かなり少ないです。
先日、1週間ほど海外に行っていたのは、高知県の産業振興推進部の輸出振興室の中の貿易協会とタッグを組んでいるもので、10年くらい前からフランスに行ったりとかインドネシアに行ったりしています。そこにアシストいただいて台湾やインドネシアにも商品が届いています。国内だと地産地消・外商課の方々の成果は高いですね。

―――アグレッシブに仕事に取り組む嶋崎さんですが、須崎で仕事をする上での課題をお話いただきました。
須崎市内の経営者は現在だいたい60歳以上。僕のように40代の経営者は珍しいです。みんな本当は海外への進出にも興味は持っているけど、尻込みしてしまっています。お金と時間をアグレッシブに使うという意味では、経済の構造を新陳代謝しないといけないなと思いますし、世界の潮流には乗りにくくなっているというのが本音です。
自分自身が30代のときは、何もしなくても出ていたテストステロンとかドーパミンを、あの手この手使って今出そうとしているけど、出したくてもなかなか出せないんです。(笑)
新陳代謝するとなると、子供はやっぱり必要。将来を担う人たちですから。だから今、家庭を疎かにはできないです。仕事もキープして貯金貯金とばかり言わずに、旅行などにも行って家族の時間を作る。かと言ってお金もなくなったら厳しいから、限られたリソースをできるだけ最適配分にすることを常に考えながら生活していますね。
―――10年前のインタビューで「須崎は額面ではない豊かな暮らしができる」とお話いただきましたが、現在はどうですか。
圧倒的に都会で暮らすより固定費が安くなりますね。都会で暮らすことで、いちばんしんどいのが家賃ですよね。それを月に4万でも5万でも圧縮できると他に回せます。都会だったら家賃を含めた可処分所得をあげるために給料を上げようと頑張る、すると、その分自分の時間が少なくなるし税金で所得もなくなってしまう。燃費が悪いというか、アクセルをすごい踏んでるけど、「あれ?あまりスピード出てない…」みたいな感じですよね。
こちらでは中古住宅でもリノベーションしたら月3万くらいで雨風しのげます。畑ができるスペースがあったら自分で野菜を作ったらいい。子供も土を触って、植物がこうやって育つんだという教育にもなるし、食品を自前化できるってことは、生活が破綻しづらくなる。それは東京ではなかなかできないと思います。
―――最後に、今後須崎でやってみたいことを教えてください。
農業していると感じるのが、秋でも台風が来なくなって水が少ないし、気温が高くなりました。地球環境の変化で今までできていたものができなくなった。持続可能な社会の実現というか、環境を変えずに済むようなビジネスを、ご縁があったりアイディアが浮かんできたら自分の残りの人生はそこにチャレンジしていきたいと考えています。今は、ぬたを冷やすのに電気代にかなりコストがかかっていて、地球の環境保護には貢献しないビジネスモデルになっています。それを抑える方向にしていかないといけない。自分の会社だけだと小さな話かもしれないですけど、みんなが目先の利益を優先して無駄遣いすると、大変なことになります。持続可能な社会の実現や自然環境の維持に向けて貢献できる事業をやってみたいです。

グローバルな仕事の話から、ご家庭の話まで、多岐に渡るお話をしてくださった嶋崎さん。たくさんの課題と向き合い、おじずに突き進む姿勢がとてもたくましいです。今後のご活躍も楽しみにしています!
(取材:2025年10月 片田・大﨑)
↓10年前のインタビューはこちら↓
「須崎市での起業は、サラリーマン時代から青写真はできていました。」兵庫県淡路島出身の嶋崎さんは、広島の自動車メーカーでサラリーマン時代を過ごし、その後、父親の実家がある須崎市浦ノ内に2010年移住。ここで、“葉にんにくのぬた”の商品開発に奔走しています。

年に1、2回程度、祖父母を訪ねて帰省していた場所、それが須崎市浦ノ内でした。ある時食べた高知県独特の葉にんにくのぬたに、衝撃的なおいしさ感じ、これを県外にも広めたいと考えるようになりました。ここ須崎で起業しようと奔走し始めたのは2008年のこと。当時、まだ自動車メーカーに勤めている頃から、葉にんにくの苗を取り寄せてみたり、室戸から足摺まで網目状に生産者を探し回ったり、試験的に栽培を始めることに。その後2012年にEarth Aid(アースエイド)を創業、2013年に法人化をし、2014年には“ぬた”の製造販売を開始しました。
もっと早く立ち上げようと考えていた会社。しかしながらそこには田舎独特のインターネットのインフラ整備の遅れが問題になりました。当時、浦ノ内はインターネット回線や携帯電話の通信環境が遅れており、2012年にケーブルテレビが市内全域カバーされたことからインターネットが開通し、これを機に起業した嶋崎さん。
「当時は、県庁まで行って、インターネット環境の悪さや早期の情報インフラの整備を訴えてきましたよ。これから若者が田舎で仕事したいって思っても、ネット環境がなければUターンもIターンも見込めないんじゃないですかって。」2008年から訴え続けたインフラが整備されたのはなんと4年後。「なんでこんなに(時間が)かかるんだって思いました。(笑)ネット環境がないと起業が出来ないと思っていましたから、もっと早くインフラが整備されていれば、起業も早かったんじゃないかなと思いますよ。」
しかしながら、このインフラ整備までの数年間も無駄にしないように耕作放棄地を探したり、専門機関に行き最新の農業技術や加工技術を研究したりと、嶋崎さんに余念はありませんでした。「いろんな栽培方法を見たり学んだりして、人が健康に暮らせる本質ってやっぱり“土”だなと思い、耕作放棄地を使って有機での葉にんにく栽培を始めることにしたんです。」
荒れた耕作放棄地の草刈りからの畑作り、何もかもが初めての農業でした。「耕作放棄地の草刈りをして、さぁここからどう耕そうかと畑でぼーっとしていると、近所の知り合いがトラクターに乗って来てくれたんです。畑の草を刈るにも、耕すにも、1人では出来なかったですね。まわりの農家さんに助けてもらいました。土地もトラクターも農具も借り物で、加工場の資材も貰いものを利用しています。」
多くの人に支えられてここまで来られたことを思い出しつつ語る嶋崎さん、須崎の人の印象についても聞いてみました。
「元々、祖父母が須崎の人なので、須崎のイメージや移住してのギャップはあまりなかったんですが、敢えて言うならラテン的なところは関西人と近いけれど、関西を基準にしたら高知県の人はシャイですね。でも2回目に会うと、人情味に溢れていてとても良くしてくれます。お酒を飲むと親睦の時間がもっと早くなります。(笑)あと、女性が仕事も家庭も両立していて、すごいなぁと思います。高知県の女性を“はちきん”と言いますが、働き者が多いですよねぇ。」
須崎の人、高知県民の人柄に固定概念なくフラットに入ることができたのは、嶋崎さんの持前のフランクなしゃべりもあったからかもしれません。そんな嶋崎さんが始めた“ぬた”の製造から葉にんにくの栽培といった、ある意味“逆6次産業”。これから6次産業をしてみたいという人へのアドバイスを聞きました。「“案ずるより、産むが易し”ですね。でも最初は不安も大きいと思いますので、色んな人と仲良くなって、情報を集める事が大事です。農業をするにも加工をするにも、補助金や技術などの情報を得るために行政や研究施設、商工会などあらゆるところを回ります。情報をいかに効率よく集めることや、人と出会いネットワークを構築し、その人との接点を大切にし、有機的につながっておくことが大事なのではないかなと思います。」
農業も6次産業も関係なく、人とつながること。地域の人には声をかけ、交流を持つことが大事と教えてくれました。そうすれば、向こうから情報を持ってきてくれたりと、地域から声がかかり始めたと言います。そして、最後にこれから移住してくる人へのアドバイスを聞きました。
「物欲が強い人はダメでしょうね。(笑)地域のお年寄りと関わったり、絆を欲している人が向いているかもしれません。エルメスが欲しいとか年収1,000万円が欲しい人には向かない。額面ではない豊かな生活をしたい人には須崎は良いところです。人は、食や睡眠が大事ですよね。日の出とともに働き、日の入りとともに眠る。食が豊かで安いですから、贅沢な暮らしはしなくていいと割り切ること。そんな暮らしをしたい人には最適です。」
(取材:2015年1月)